フレネルレンズのスポットライトについての解説です。
「フレネル」とは、フランスの物理学者の名前です。
分類上は「灯体 > スポットライト > レンズによる集光 > フレネルレンズ」となります。
(詳しくは「光学系による灯体分類」の記事をご覧ください)
| フレネルレンズのスポットライト | ||
 |  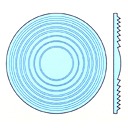 | 仕込み図の記号 |
光の特徴と使われ方
フレネルレンズスポットライトから出る光は、
- 輪郭のボンヤリとした (=ソフトエッジの) 被照面を作る
- 影がやや薄く出る (特に、照射範囲を広げて使う場合)
- 遠い距離から照らすと、光が散らばっていきやすい
という特徴があります。スポットライトの中では、ややフラッドライトに近い傾向を持つライトです。

小川昇(1996)『光のデッサンから舞台照明のつくり方まで』p.15では、スポットライトとフラッドライトの中間として扱われています。
このため、
- 舞台の真上や斜め上から、舞台の広い範囲を均等に照らす目的
…「ナナメ(ブッチ)」「トップ(狭義の”地明かり”)」など - 舞台のある部分を際立たせたいが、輪郭のクッキリした光を嫌う場合
…「○○エリア」など - その他、とりあえずスポットライトが欲しく、かつ輪郭がボンヤリしていてもよい場合
…「SS」「コロガシ」「PARライトの代用」など
…などの目的に使われます。
また、フレネルレンズのスポットライトは総じて軽量・小型の機種が多いのが特徴です。このため、
- 天井が低い小劇場
- 機材ごと車で移動するようなツアー公演
でも、好んで使われます。
特に小劇場では、大劇場なら平凸が多用される「シーリング」や「フロントサイド」に相当する明かりも、フレネルで作ることが多いです。
有名機種とニックネーム
フレネルレンズの代表機種としては、
- 丸茂電機 / DF
- 丸茂電機 / FQ
- 丸茂電機 / HQE(ハイベックス)シリーズ
- RDS / Q-spot
などがあります。また、コロガシ専用灯体である 丸茂電機 / FP も、フレネルレンズです。
フレネルレンズは平凸レンズに比べると有名機種が多く、丸茂電機のMF (国産最初期のフレネル)、DF、FQなどは代名詞化され、後継機種 (FQF、FQHなど) や、他社の類似機種までこの名前で呼ばれることがあります。
このため、劇場の機材リストにDFやFQと書いてあっても、本当に自分が知っている「DF」や「FQ」と同じものかどうか、確認が必要です。
平凸っぽいフレネル?
通常、フレネルレンズのスポットライトと言えば、「光の輪郭がボンヤリしたスポットライト」と紹介されるのが普通ですが、そうではない、比較的クッキリした輪郭の光を出すフレネルレンズも、少数ながら存在しています。
実は、フレネルレンズが輪郭のボンヤリした光を出せるのは、レンズの裏側に網目のようなデコボコを作り、それが「ぼかしフィルター」の役目を果たしているからです。

ということは、裏面の網目加工をしていないフレネルレンズは、平凸レンズに近い、比較的輪郭のクッキリした光を作ることができる、ということです。
このようなフレネルを、特に「ハードエッジフレネル」と呼んで区別することがあります。
ハードエッジフレネルの灯体は、丸茂電機 / CEF 、丸茂電機 / HQE(ハイベックス)シリーズのハードタイプ、などがあります。
ただ、普通のフレネルに比べるとマイナーな存在なので、このブログでも特に明記しない限り、フレネルという言葉は、普通のフレネル(裏面網目加工をしたフレネル)という意味で使います。

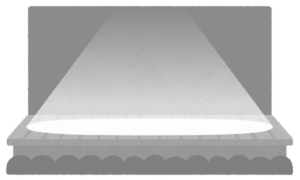






コメント